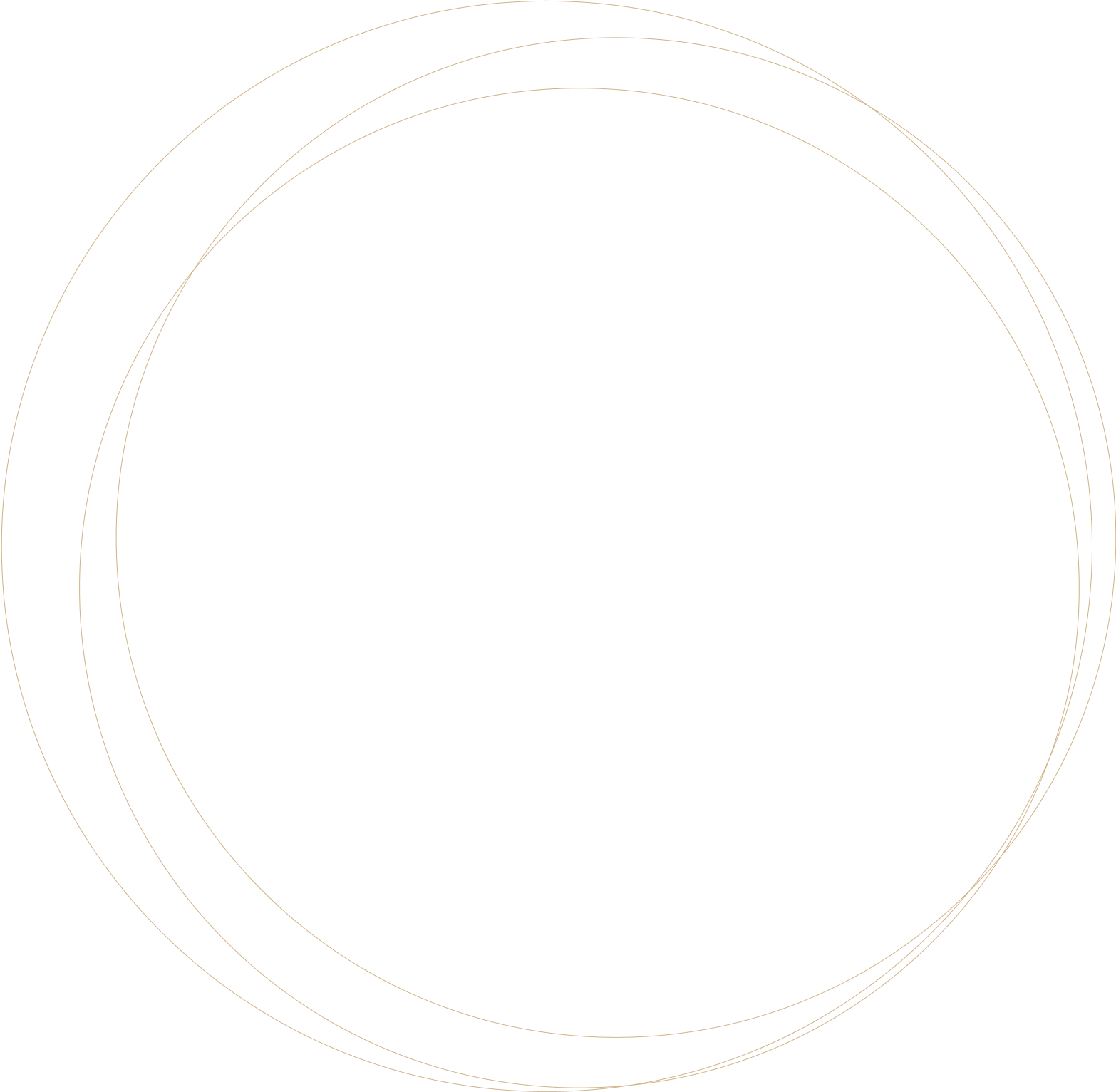親の終末期医療を“一人で背負わない”ために
親が高齢になると、いつかは向き合わなければならないテーマがあります。
それは介護や相続だけでなく、「終末期にどのような医療を望むのか」という意思決定です。
しかし現実には、その話題を家族で十分に話し合えているケースは多くありません。
特に兄弟姉妹がいる場合、「誰が決めるのか」「どう切り出すのか」が曖昧なまま、時間だけが過ぎていきます。
高齢者の終末期医療とは
終末期医療という言葉から、
命が脅かされている状況で「延命治療(心臓マッサージや人工呼吸など)をするかしないか」
という二択を想像して、高齢者と終末期医療が結びついていない方も多いかもしれません。
たとえば、元気だった子どもが突然事故にあった場合、
「できる限りの治療を」と迷わず願うのが自然でしょう。
一方で、高齢者の場合は事情が大きく異なります。
突然の交通事故ではなく、だんだんと元気がなくなってきた状態で意識がないという場合、どう考えたらいいでしょうか。
高齢者の場合、治療に体が耐えられるのか、
それを「回復」と呼べるのか、
その先にどのような時間が残されているのか――
簡単には判断できない要素が重なる中
「できる限りの医療」とは、どこまでを指すのでしょうか。
年齢や状況だけでは判断しきれない場面が多く、
その場で初めて会った医療者が重大な決断を下すことはできません。
家族が突然、決断を迫られる場面
たとえば、私自身もこんな経験があります。
施設に入居中で、要介護5・認知症を患っている80代後半の母が、
ある日突然、血圧が大きく低下して反応がないという連絡を受けました。
施設からは
「救急搬送を検討していますが、よろしいでしょうか」
と電話があり、急激な変化だったこともあり、私は「お願いします」と判断しました。
救急病院に運ばれた母は、重度の脱水と診断されました。
医師から点滴による治療が提案され、実際に点滴を行ったことで状態は改善し、
約2週間の入院を経て、無事に施設へ戻ることができました。
良かったと思う一方で、私は立ち止まって考えました。
母はすでに、自分の意思を言葉で伝えられる状態ではなく、車椅子での生活です。
脱水が改善したからといって、要介護5は変わりありません。
そんな中、救急搬送をお願いし施されたこの医療は、
点滴治療だけでなく、全身の画像検査や集中管理、
連日の検査、リハビリの評価、24時間の看護体制など、
いわゆる高度な救急医療が一通り行われました。
日常生活を支えるための、ごく自然な医療を望むのであれば、
救急搬送され、救命救急病棟で高度な医療を受ける――
これらのすべては過剰な医療だったのではないか…
わたし自身、看護師としてがんセンターで多くの患者さんの生と死に向き合い、数えきれないほどの意思決定に関わってきた自負があります。
そんな私でさえ、
「本当に母が望んだ選択だったのか」と、簡単に答えを出すことはできませんでした。
結果として、退院後は施設のスタッフが温かく迎えてくれ、
24時間対応の訪問診療と訪問看護を導入することができました。
今後は、救急医療に頼ることなく、自然な経過で過ごすという選択肢を持てたことに、私は大きな安堵を感じました。
高齢者の終末期医療の判断は「グレーな選択」の連続
高齢者が、年齢相応に徐々に気力や体力を失い、命の期限が見えてくるような状況での「終末期医療」の判断は、こうしたグレーな場面の連続で、細かな選択の積み重ねです。
先ほどの事例のように、白か黒かでは割り切れない選択を、家族が突然迫られることを覚悟する必要があります。
親が高齢であるにも関わらず、「この世からいなくなる(命がなくなる=死ぬ)かもしれないこと」を今まで全く考えたことがないために、「できる限りの治療をお願いします」と思わず口に出してしまう家族に何度も出会ったことがあります。
晴天の霹靂なのですから、それを責めることはできません。
「一人で背負わない」ために、事前にできること
このような判断を「一人で背負わない」ためにも、
そして「その場の感情だけで決めなくてすむ」ためにも、
事前に意思を言葉にしておくことの意味は大きいのです。
そのためのツールの一つが、エンディングノートです。
医療は専門性の高い分野であり、家族だけで背負うには重い判断が求められます。
だからこそ、元気なうちに「どんな最期を迎えたいのか」を言葉にしておくことが、家族を助けることにつながります。
まずは、自分が書いてみるという一歩
そうはいっても、親にエンディングノートを勧めることに、ためらいを感じる方も多いでしょう。
「急にそんなことを言い出すなんて、私のお金(土地)を狙っているのか?」
「認知症に備える? 私がそうなると思っているのか? バカにするな!」
「死ぬことを考えるなんて縁起でもない」
「うちの子どもたちはきょうだい仲もいいから、もめるなんて考えられない。いざという時はみんなで考えてやってくれればいいよ」
「私のことを一番よく知っているのはおまえだから、あとは任せる」
そんな声を実際に聞きますし、親の反応をあれこれ想像するだけで二の足を踏んでしまう方も多いです。
そんなときは、まずあなた自身がエンディングノートを書いてみることをおすすめします。
エンディングノートは、自治体配布のものから書店で購入できるものまで、さまざまな種類があります。
実際に手に取って書いてみることで、自分の価値観に気づくきっかけになります。
「わ、空欄ばかりで書くところが多いな…」
「最初の1ページ目からもう書けない…」
「今まで考えたこともない内容だから、難しい」
「気が重い…」
そうした戸惑いを通して
「もし私だったら、誰に任せたいだろう」
「どこまで医療を望むだろう」
ということを具体的に想像して、自分の人生を、家族との関係を思いめぐらす機会になります。
自分の価値観を言葉にすることで、初めて家族との会話の準備が整います。
エンディングノートは、相続や葬儀のためだけのものではありません。
終末期医療という重い判断を、家族に丸投げしないための大切なツールです。
まずは、自分でエンディングノートを選んで実際に書いてみる。
「私は、何を決めていて、何を決めていないのか」に気づく時間が、親の意思を聞く準備となるのです。
それは人生の終わりを考えるためのノートではなく、
人とのつながりを見つめ直す時間なのかもしれません。
そんな意味で私は、この取り組みは単なる「エンディングノート」ではなく、
人との関係性を見つめ直すための「縁(えん)ディングノート」と呼びたいと思っています。