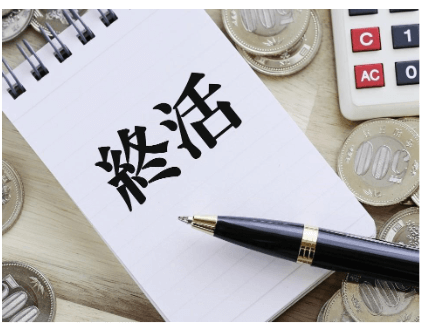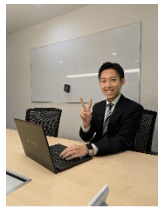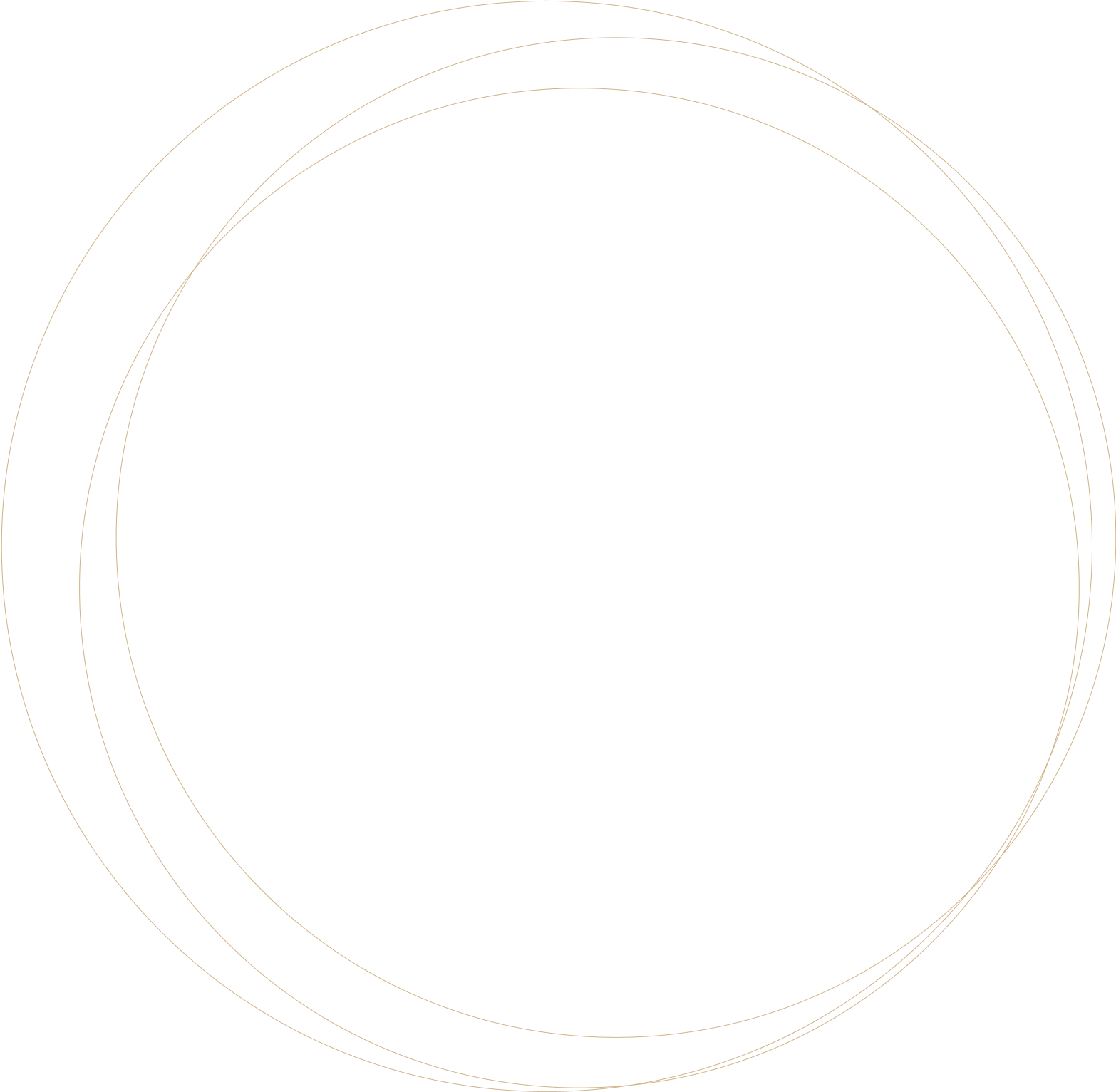1 「死」とは無縁の大学生
希望に満ちた大学4年生の時、私は「就職活動」を一切せずに、行政書士国家試験に挑み、無事一発合格しました。今思えば、背水の陣。人生最大級の無謀な挑戦だったと思います。周りの大人の皆さんからすれば、かわいらしい若気の至りかもしれません。私自身も人とは違う選択をした自覚は十分にありました。将来への不安はありつつも、未来への希望に満ちていた当時の私にとって、「死」は遠い世界の出来事。まだ若いから、明日死ぬなんて考えない。きっと誰でもそうでしょう。
しかし、親を不安にさせながら行政書士の勉強に打ち込んでいた大学4年の秋、私に「死」を強烈に意識させる出来事が起きました。母方の祖母の他界です。
2 突然の別れ、そして後悔
祖母は私が小学生の頃に脳梗塞を患い、自宅で倒れ、入院と退院を繰り返していました。次第に病状は悪化し、認知症や骨折も患い、祖父や母との家族仲にも亀裂が入ることに。小学生だった私は、詳しい事情もわからないまま、祖母とは会わない日々が10年ほど続きました。
ある日、父から「おばあちゃんの容体が良くないから、病院に来てほしい」と連絡がありました。兄と私は急いで病院に向かいましたが、父が連絡をくれた時点で、祖母はすでに息を引き取っていたのです。
10年ぶりに再会した祖母は、冷たい遺体安置室に横たわっていました。10年前とは比べものにならないほど老け、もう二度と動くことはありません。その姿を5分ほど見つめ、ようやく涙が溢れ出しました。幼い頃、世界一おいしいご飯を作ってくれた、大好きだった祖母との再会が、まさかこんな形になるとは。私は我を忘れて泣き続けました。
3 大好きなおばあちゃん
小学生のころ、おばあちゃんの家に兄弟二人で泊まることがよくありました。おばあちゃんは決して裕福な暮らしではありませんでしたが、それでも世界で一番料理がうまいと評判でした。戦後復興期に作られた小さな団地で、古いキッチン、調味料は味の素。それなのに、到底理解が及ばぬほどに料理がおいしかったのです。おばあちゃんのつくる世界一しょっぱい梅干し、他にもたまごやき、からあげ、鶏レバー。おばあちゃんのせいで、いまだにスーパーで売っている梅干しはひどくまずく感じます。おばあちゃんのおかげで、好みが分かれるレバーが大好きです。おやつの時間にフライドポテトを作ってくれたことは忘れようもありません。兄と私はいまだに、フライドポテトは家で作れるということを知ったのはあの時だったなとお互い話すことがあります。
そんな大好きだったおばあちゃんの『死』は私に生きているということを強烈に実感させました。
4 祖母の死が教えてくれたこと
祖母が他界した後、遺産相続の手続きは母と叔父が地元の司法書士に依頼し、進んでいきました。私は行政書士試験の勉強中でしたから、「あと数年、祖母の死が遅かったら」「あと数年、自分が大人になっていたら」と悔やみました。専門家として、大好きな祖母に恩返しができたかもしれないのに、と。
祖母の死まで、民法が苦手だった私は行政書士といえば「許認可」だと思っていました。しかし、祖母の死をきっかけに、相続の専門家になることを決意したのです。
相続の世界は奥深く、不動産、生命保険、銀行、証券、医療、介護など、多岐にわたる知識と業界との連携が求められます。そして、その世界に身を置いて一番驚かされ、そして学んだことは、生前の相続対策と終活の重要性です。
5 若者にこそ知ってほしい「終活」
世界的な人気を誇る日本の漫画『NARUTO―ナルト―』の中に、私が好きなキャラクター「うちはイタチ」の言葉があります。
『死に際になって自分が何者だったか気付かされる』
これは、「死んだ後にどうなるか」ではなく、「どう生きてきたか」を問うているのだと私は解釈しています。
「相続」と聞くと、「死後のこと」と考えがちですが、それは違います。相続は、生きている間にどう備えるかが鍵を握るのです。自分の死後なんてどうでもいい、という方には私の話は響かないかもしれません。しかし、自分の人生に意味を見出したい、大切な人に最高の最期を見せたい、そう思うのであれば、今すぐ相続対策を考えるべきです。
特に、私がその重要性を訴えたいのは、若い世代の皆さんです。
日本は少子高齢化が進み、今後、様々な業界が衰退していくことが予想されます。しかし、相続の需要は今後ますます高まっていくでしょう。2030年には団塊の世代が相続にかかる世代となり、さらに市場は拡大すると言われています。上の世代が終活や相続対策を怠った結果、その「尻拭い」をすることになるのは私たち若い世代です。
そうならないためにも、愛する家族が元気なうちに、私たち若い世代が率先して学び、伝え、実践していくことで、終活の重要性を上の世代に伝えることができるのです。終活は、残す人も、残される人も、誰もが幸せになれる選択なのです。
6 まずはエンディングノートから始めよう
いきなり専門家に相談したり、遺言書を書いたりするのはハードルが高いと感じるかもしれません。だから、まずは「エンディングノート」を親子で書いてみることをおすすめします。エンディングノートは、財産のことだけでなく、自分の好きなものや思い出、生きてきた軌跡である「自分史」など、気軽に書き始められるものです。
相続は「死」ではありません。どう生きるか、どう最期を迎えるかを考えるのが「終活」です。そして、その終活の入り口として、エンディングノートは最適です。
私は大学時代、まったく「就活」をしませんでした。その結果、新卒で入った会社をわずか9ヶ月で辞めるという情けない失敗を経験しました。同じ失敗はもう二度としないし、後悔もしたくありません。だから私は、23歳という若さで、死ぬ予定は今のところありませんが、今度こそ「終活」をして、どう生きるか真剣に考えたいと思います。
それがいつか、大好きだったおばあちゃんへの恩返しになることを祈りながら。