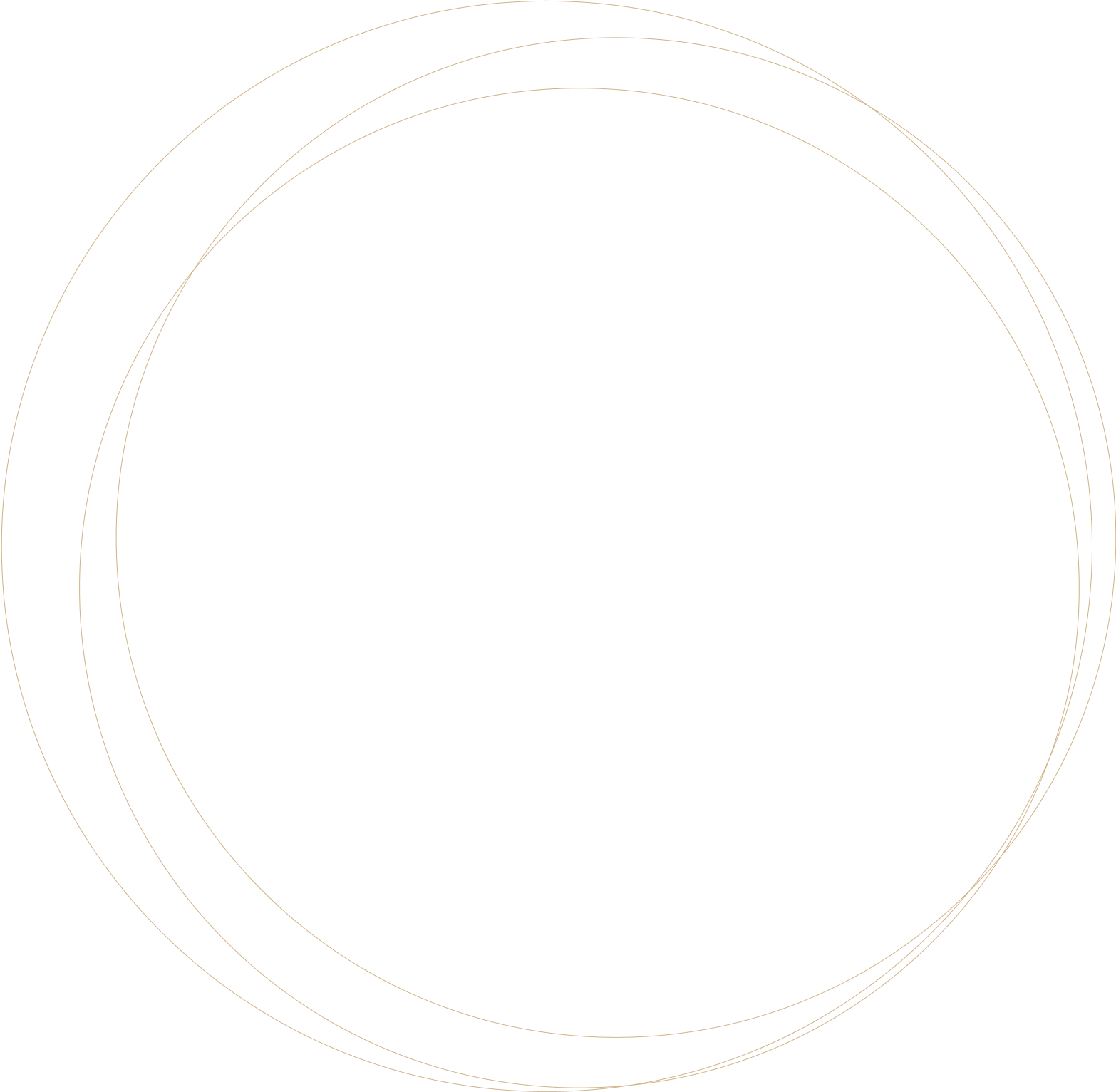税理士が「エンディングノート」について話すのは、少し意外に思われるかもしれません。私たちの仕事は、相続税の申告や対策など、財産という「目に見えるもの」を扱うことが中心だからです。しかし、本当にそれだけでよいのでしょうか。この問いと向き合ったとき、私は「縁ディングノート」と出会いました。
縁ディングノートの「縁」には、人と人とのつながりが込められています。自分の人生を書き残すことは、自分自身を見つめ直し、大切な人へ想いを伝えることにつながるのです。税理士として縁ディングノートに関わるようになった今、それは私のライフワークの一つとなりました。

2つのセミナー、それぞれの「縁」
現在、私は2種類の縁ディングノートセミナーを開催しています。
一つは、終活や相続対策を考えるシニア世代向けです。お寺の落ち着いた空間で行うこのセミナーには、「何か始めたいけれど、何から手をつければいいか分からなかった」という方が多く参加されます。
これまで懸命に生きてきた人生を振り返り、これからの人生を自分らしく生きるために、そして家族や大切な人たちへ想いを残すために、縁ディングノートは最適なツールです。ノートを一緒に書き進めるだけでなく、相続の知識、具体的な事例も交えながら、終活全般についてもお伝えしています。
毎回、終活や相続の専門家にもお越しいただき講義をしていただいていますが、参加者の質問が絶えません。このセミナーをきっかけに、実際に終活や相続対策に踏み出す方もいらっしゃいます。
もう一つは、30〜40代の方向けです。日本では「死」について語ることを避ける傾向があるように感じています。しかし、これから先の長い人生を歩む世代だからこそ、「死」について考えることが、今を本気で生き、自らの人生をより大切にすることにつながると考え、このセミナーを始めました。
ここでは、これまでの人生を棚卸し、未来をどう生きるかを考えます。その結果を記すのが縁ディングノートです。可能であれば、書いたノートをご家族、特に親御さんに渡すことをお勧めしています。それがきっかけで、ご家族もノートを書き始めることを期待しています。
興味深いのは、ご参加の方がそれぞれ、まるで宝探しでもするかのように熱心に書く項目が違うことです。「自分のこと」をじっくりと書き込む方もいれば、「お気に入りのお店」のページに夢中になり、目を輝かせながらペンを走らせる方もいらっしゃいました。セミナー最終回の後、参加者のお一人のお気に入りのお店で懇親会を開催したところ、以来それが恒例になりました。また、参加者で作るLINEグループでは、セミナーで感じたことや今後の目標などを共有し合い、自然とコミュニティが誕生しています。
顧問先で気づいた「税理士だからこそできること」
セミナーを続ける中で、顧問先でも縁ディングノートの重要性を実感する出来事がありました。
ある日、顧問先の80代の会長ご夫妻から「先生はエンディングノートをご存じですか」と尋ねられたのです。セミナーを開催して縁ディングノートの力を伝えているのに、日頃から大切にしているお客様に何も伝えられていなかったと、ハッとしました。
それ以来、毎月の訪問時に30分ほど、ご夫妻と一緒に縁ディングノートを書き進めています。このご夫妻の相続対策はお手伝いしていましたが、財産という目に見える部分にだけ注目し、お二人の想いという目に見えない部分には触れられていなかったことに気づかされました。
また、ある40代の経営者からは「自分が亡くなったら会社や家族はどうなるのだろう」と相談を受けました。会社の財務や事業承継といった目に見える対策とは別に、ご自身の想いや人生の歩みにも意識を向けていただきたいと願い、縁ディングノートをお渡ししました。ちょうどマスコミで縁ディングノートを目にされた後だったとのことで、今熱心に取り組んでくださっています。
別の50代経営者からは、「離れて暮らす両親のことを何も知らない」という悩みを打ち明けられました。ご両親用に縁ディングノートをお渡しした直後に、お母様が急逝され、「もっと早くお渡しできていれば」と悔やまれました。今はお父様がノートを書き続けておられるとお聞きしています。
想いと財産を未来へつなぐ架け橋に
「終活」や「相続対策」という言葉を聞くと、どこか遠い未来のことのように感じられるかもしれません。しかし、それは「未来の自分」と「大切な人たち」へ、今日から始められる贈り物です。
財産という目に見えるものは、専門家である私たちが整理できます。しかし、ご自身の生きた証、そして「ありがとう」という心からの想いは、書き残さなければ誰にも伝わりません。
私は税理士として、想いと財産、その両方を未来へつなぐ架け橋になりたいのです。経営者の方の生きた証を、次の世代へと確かに伝えていくために。そして、相続税という亡くなった後の税金に携わる者として、財産だけでなく想いも伝えられるように。