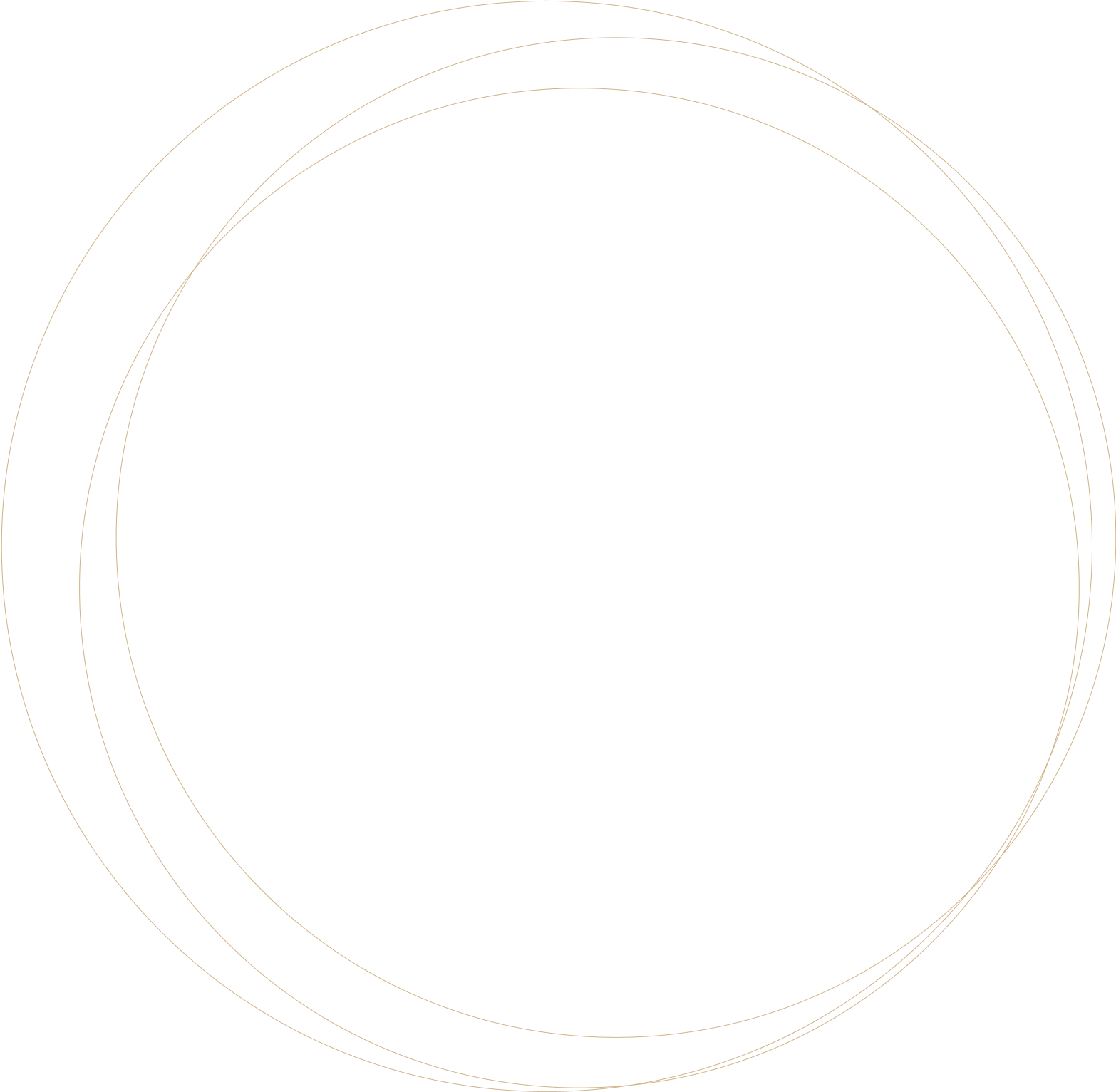秋分の日を中心に行われる「秋のお彼岸」。昼と夜の長さが同じになるこの時期は、此岸(この世)と彼岸(あの世)が最も近づくとされ、ご先祖さまへの感謝を形にする大切な行事です。
春にもお彼岸はありますが、意味合いは少し異なります。春彼岸は「未来への祈り」、秋彼岸は「これまでの実りへの感謝」。自然のサイクルと重ね合わせ、日本人は春と秋の両方に祈りと供養の時間を設けてきました。
なぜ秋は「お萩」なのか?
秋のお彼岸には「お萩」をお供えします。材料はもち米と小豆ですが、その呼び名や作り方に季節感が込められています。
春:牡丹の花の名にちなみ「ぼた餅」。華やかなこし餡で。
秋:萩の花にちなみ「お萩」。素朴な粒餡で。
秋の小豆は新物で皮が柔らかいため粒餡にしやすく、春は冬を越えて皮が硬くなるのでこし餡にする――食材の特性も背景にあります。単なる呼び名の違いではなく、自然の恵みと人の知恵が結びついた習わしなのです。
お萩は供えた後に家族で食べます。これを「供養の分かち合い」と呼び、ご先祖さまと家族をつなぐ大切な行為とされてきました。つまり、お萩は「命のつながりを味わう象徴」なのです。
行事を通して「心」を伝える
お彼岸は、単なる供養や習慣ではなく、「ご先祖を想い、自分の生き方を振り返り、次の世代へと心をつなぐ」時間です。
しかし現代は核家族化が進み、行事の意味が形骸化してしまうことも少なくありません。「なぜお萩を供えるの?」「どうして春と秋にお彼岸があるの?」――子どもや孫から聞かれても、答えられない大人は意外と多いものです。
だからこそ、こうした行事の意味を子々孫々と伝えていくことが大切なのです。お彼岸という機会に、家族が集まったらぜひ「この行事に込められた想い」を語り合ってほしいと思います。
縁ディングノートに託す“行事の意味”
縁ディングノートは、財産や医療の希望を書くためだけのものではありません。自分が大切にしてきた価値観や、家族に伝えたい想い、そして「行事や風習の意味」も書き残すことができます。
例えば――
「秋のお彼岸にはお萩を供え、家族で分け合うことを大切にしてきました」
「祖母から受け継いだ習慣なので、これからも続けてほしい」
「集まるときには、この行事の意味を孫たちにも話してあげてね」
こう記しておけば、家族は行事をただ繰り返すだけでなく、そこに込められた「心」まで受け取ることができます。
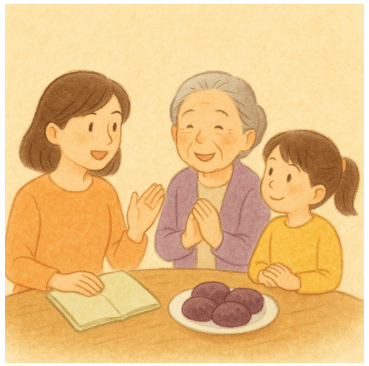
未来への贈り物として
春と秋、二度あるお彼岸は「祈り」と「感謝」をつなぐ時間。そしてお萩は「命の連続性」を味わう供え物。そこに込められた意味を知ることで、行事はただの習慣ではなく、家族の心を結ぶ「縁」へと変わります。
どうか今年のお彼岸には、お萩をお供えしながら、家族にこう伝えてみてください。
「これはご先祖さまへの感謝の印なんだよ。そして、この習慣をこれからも大事にしてほしい」
その言葉を縁ディングノートに残すことは、未来の家族への何よりの贈り物になるはずです。
(文責:一橋香織)