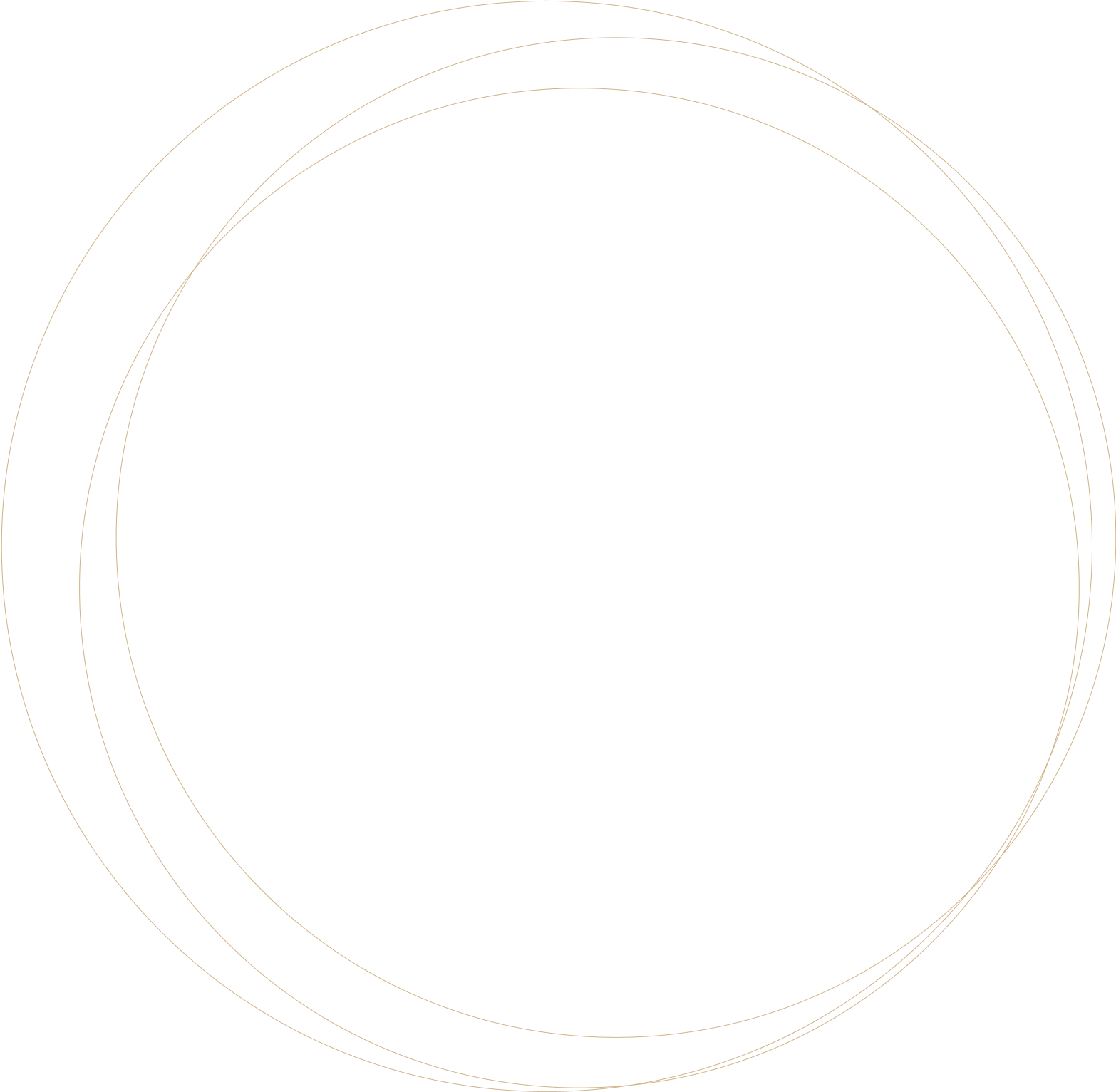筆者の友人が亡くなった。
50代、独身、ひとり暮らし。原因は、長年の飲酒習慣による身体の限界だった。
彼は明るく、社交的であった。複数の地域コミュニティに参加し、会話もうまい。とても「孤独死」するようなタイプには思えなかった。
しかし、ひとり暮らしであれば誰でも可能性があることを、筆者は身に染みて感じた。誰かに看取られることなく、静かに命が終わっていたのだ。
筆者は終活や相続、孤独死の現場に携わる専門家であるにもかかわらず、友人として傍にいただけで、準備のひとつも進めることができなかった。
内閣府の調査によれば、年間で「孤立死」と位置づけられる人は2万人を超え、そのうち約8割が男性である。特に50代から、孤独死は急激に増加している。
社会的には「まだ若い」「備えなんて早い」と思われがちな年齢だが、現実はそうではない。
彼は「孤立死」には該当しない。人間関係もあり、仕事もしていた。しかし、亡くなったとき、すぐに気づける人はいなかった。
たとえ人とのつながりがあっても、「日常的な気づき」がなければ、孤独死は誰にでも起こり得るのだ。
「備える」とは、死の準備ではなく、生の安心のためにある
亡くなった彼に対し、筆者は何ができたのか──
そう考えたとき、真っ先に浮かんだのが「エンディングノート」であった。
とはいえ、エンディングノートは「死んだあとに家族が読むもの」と誤解されがちだ。
だが実際には、それだけにとどまらない。
むしろ、「生きている今」を支えるための安心ツールでもある。
たとえば、彼のように相続人がいない人にとって、
・どんな財産があり、
・どんな契約を結んでおり、
・どのような形で整理してほしいのか──
それらをあらかじめ可視化しておくだけで、死後に関わる人たちの負担は大きく減る。
さらに言えば、誰に何を託すか、葬儀はどうしてほしいかといった「意思の表明」もまた、自分自身の不安を軽減する材料となる。
彼には資産もあり、人脈もあった。だが心のどこかで、「自分が死んだらどうなるのか」という不安を抱えていたように思える。
それが酒という逃げ道に繋がっていたのだとすれば──
エンディングノートが、その不安を受け止める役割を果たせたのかもしれない。
50代の「まだ早い」という油断
彼はビルのオーナーだった。
資産はあっても、相続人はいない。
「まだ元気だから」と何も着手しなかった。
その油断が命の終わりとともに、すべてを「誰かに任せる」ことになってしまった。
彼のような資産家の場合、遺言がなければ、いずれは家庭裁判所により「相続財産清算人」が選任され、死後の手続きが進められることになる。
手間も時間もかかり、専門知識も求められる。財産が多いからこそ、その「手続きの重み」も大きくのしかかる。
身近な友人や、遠い親戚、テナント、役所、税務署、遺品整理業者、不動産業者、リフォーム業者など──
彼が意図しなかった人たちにまで、さまざまな負担がかかる可能性があるのだ。
準備をしなかった人生は、不幸だったのか?
筆者は、彼の人生が不幸だったとは思っていない。
何度も酒を酌み交わし、心から笑い合った。
専門家として力にはなれなかったが、友人として彼の人生に少しでも楽しさを添える存在でいられたのなら、それだけで十分だとも感じている。
ただ──
もし彼が少しでも「備え」の知識を持ち、エンディングノートでも遺言でも、自分の想いを残していたら。
そこには、また違った未来があったのかもしれないという思いが、今も筆者の胸に残っている。
エンディングノートは「人生の説明書」
「エンディングノートなんて、意味があるのか?」
そんな声を耳にすることもある。
だが、筆者は思う。
エンディングノートは「死後のための書類」ではなく、自分の人生を他人にわかりやすく手渡すための説明書であり、書くことで自分の人生を形作る手助けをしてくれるものだ。
人生は長いようで、あっという間に過ぎてしまう。
だからこそ、「自分がどう生きてきたか」「何を大切にしているのか」「これからどうしてほしいのか」を今のうちに書き留めておくことには、大きな意味がある。
それは時に、命を守る手がかりになり、
時に、家族や友人の心の拠り所となり、
時に、資産や契約を守る盾にもなる。
孤独死が「不幸」かどうかを決めるのは、亡くなったという事実ではない。
生きているうちに、どれだけ備えが整っていたか──
それこそが、その人の死を「豊かな最期」に変える鍵になるのではないだろうか。
最後に──「おひとり様」への眼差しを変える
「おひとり様」と聞くと、どこか寂しげな印象を持たれがちである。
だが、それは本質ではない。
家族がいても孤独な人もいれば、ひとりでも豊かな人もいる。
大切なのは、肩書きでも立場でもなく、「どう生きて、どう終わりたいか」を自分で考え、言葉にし、行動に移していくことだ。
筆者は、もう二度と大切な人を何の準備もなく見送ることのないよう、そして、自分自身の人生にも責任を持てるよう、エンディングノートという小さな「人生の説明書」を、多くの人に伝えていきたいと考えている。
それが、彼が教えてくれた「備えの大切さ」への、筆者なりの答えである。