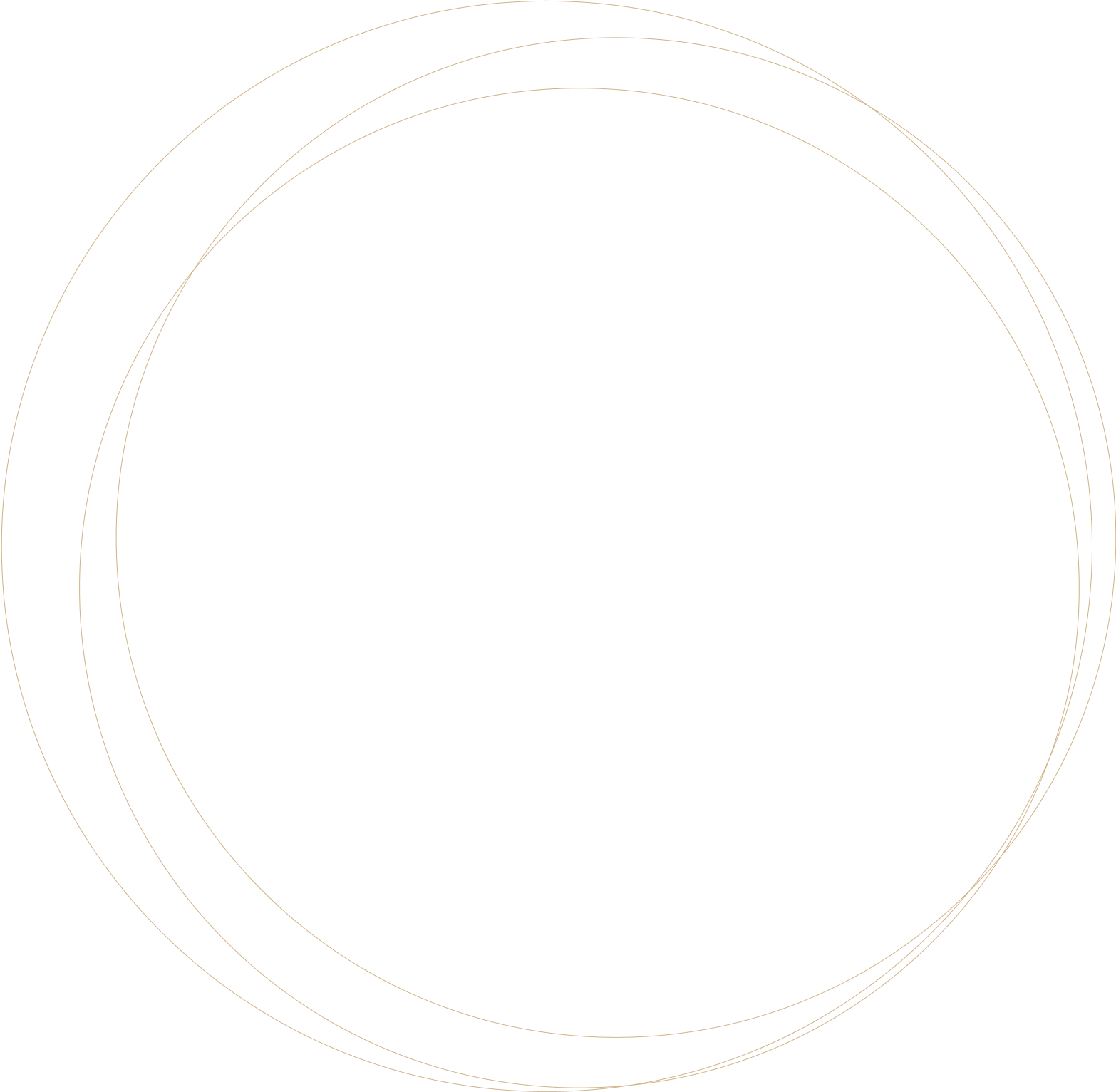7月または8月の半ば、全国のあちこちで見かける“お盆”の風景。
帰省ラッシュに混み合う駅や高速道路、迎え火や提灯のあかり、
久しぶりに集まる家族の笑い声……
でも、ふと立ち止まって考えてみると、
「お盆って、なんのためにあるの?」
「なぜ、お墓参りをするの?」
と首をかしげる人も少なくありません。
今日はそんな“お盆の本当の意味”を、今一度見つめてみませんか。
お盆のはじまり:仏教と祖霊信仰が結んだ「ご縁」
お盆は正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼ばれます。
これは仏教の経典『盂蘭盆経』に記されたお話に由来しています。
ある日、釈迦の弟子・目連尊者(もくれんそんじゃ)が亡き母の苦しむ姿を神通力で知り、
母が“餓鬼道”に堕ちて飢えに苦しんでいることに心を痛めます。
そこで釈迦に相談したところ、「僧侶に施しを行い、その功徳を母に回向するように」と教えられました。
そのとおりに施しを行った結果、母は救われた——これが盂蘭盆会のはじまりです。
この仏教行事が、日本古来の祖霊信仰と融合し、
「ご先祖さまの霊が一年に一度帰ってくる期間」として、
お盆という風習が根づいていきました。
お盆の行事と意味:迎える・供える・送る
お盆には、地域によって異なるさまざまな風習がありますが、
共通するのは「ご先祖さまをお迎えし、もてなし、そして見送る」という流れです。
▷ 迎え火(むかえび)
13日の夕方、家の門口や玄関先で小さな焚き火を焚いて、
ご先祖さまが迷わず帰ってこられるように“道しるべ”を灯します。
昔は麻の茎(おがら)を使って焚いたものです。
▷ 精霊棚(しょうりょうだな)や盆提灯
家の中には「精霊棚」と呼ばれる祭壇を設け、位牌や供物、キュウリの馬やナスの牛などを飾ります。
馬は早く帰ってこられるように、牛はゆっくり戻っていってほしいという願いを込めて。
盆提灯の柔らかい灯りは、ご先祖の魂をやさしく迎える灯火です。
▷ 供養とお墓参り
家族そろってご先祖の墓を訪れ、花や線香を手向けて祈りを捧げます。
これは“供養”という行為そのものでもあり、
私たちがご先祖の存在を忘れずにいることを伝える、大切な儀式です。
▷ 送り火(おくりび)
15日〜16日頃、ご先祖さまを見送るために再び火を焚き、
「また来年も来てくださいね」という感謝と願いを込めて送り出します。
京都の「五山の送り火」や、各地の灯籠流しなどもこの風習に通じています。
「誰のため」のお盆なのか?
「お盆って、ご先祖さまのための行事なんですよね」とよく言われます。
でも、私はこう思うのです。
お盆は、ご先祖と“今を生きる私たち”をつなぐ時間。
つまり、私たち自身のための行事でもある。
普段はなかなか意識しないご先祖の存在に思いを馳せることは、
自分がどこから来たのかを振り返ること。
そして、これから家族としてどう在りたいかを考えるきっかけにもなります。

お盆こそ、“語り合う時間”に
せっかく家族が集まるお盆。
「おばあちゃんが好きだったおやつ、覚えてる?」
「おじいちゃんの若い頃の写真、見てみようか」
そんな他愛ない会話の中に、
家族の記憶がよみがえり、心がぽっと温かくなる瞬間があります。
現代はSNSやAIで便利になった一方で、
家族で「向き合って話す時間」が減っているようにも感じます。
だからこそ、お盆の数日間は、スマホを置いて、
目の前の家族と、ご先祖の物語を語り合ってみませんか?
そして、自分自身の“未来”も見つめる
ご先祖さまのことを思い出し、
家族の絆を感じるこの時期だからこそ、
「じゃあ、自分は何を残したいのか」
「どんなふうに、家族に感謝を伝えていきたいのか」
そんな“未来”にも、心を向けてほしいのです。
縁ディングノートは、
そうした思いを記し、かたちにするノート。
単なる終活ではなく、
「ご縁」をつなぎ、「想い」を残すアイテムです。
最後に——お盆は、“感謝”と“再確認”のとき
ご先祖さまに「ありがとう」と伝える。
そして、今そばにいる家族に「いてくれて、ありがとう」と言える時間。
それが、お盆の本当の意味だと、私は信じています。
どうか今年のお盆が、
ご家族にとって“過去と未来を結ぶ”かけがえのないひとときになりますように。
(文責:代表理事 一橋香織)